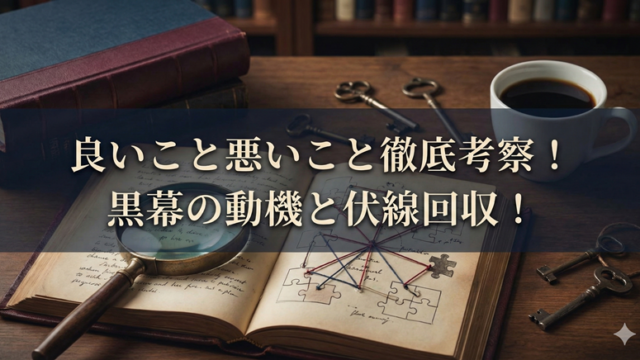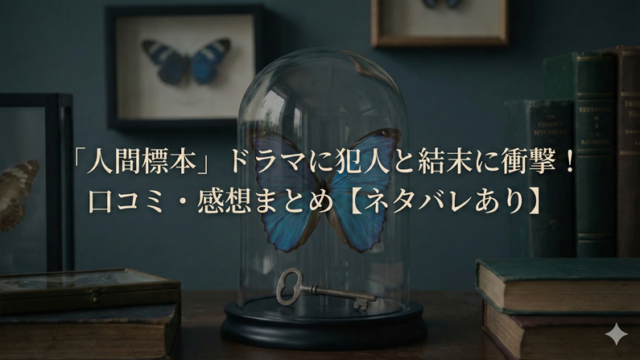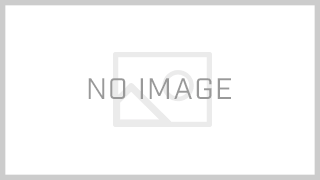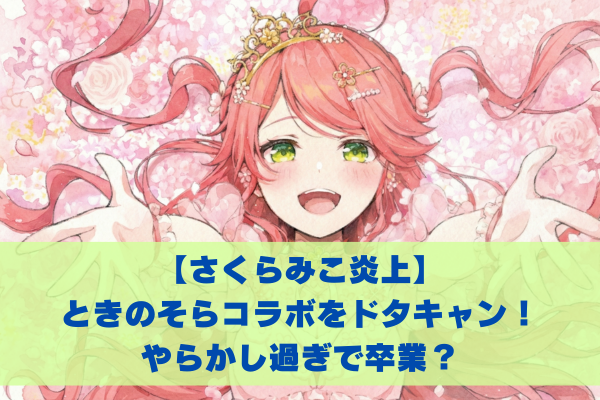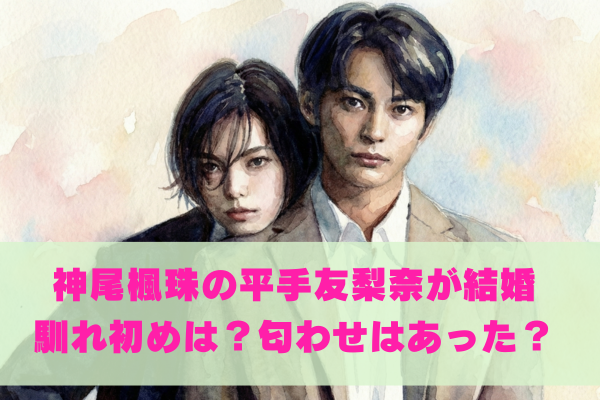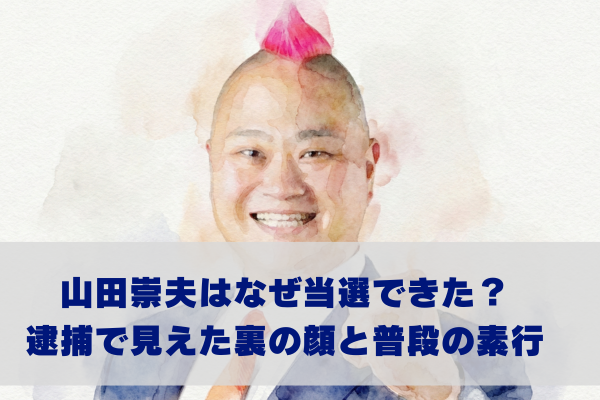ドラマ『良いこと悪いこと』で話題を呼ぶ“7人目の博士”。
名前だけの登場なのに、なぜここまで注目されているのか?
その正体には誰もが気づかなかった視点が隠されています。
られた存在に込められた意味とは――。
物語の裏に潜む意外な仕掛けに迫ります。
ドラマ『良いこと悪いこと』のストーリー

引用:ドラマ「良いこと悪いこと」
ドラマ『良いこと悪いこと』、今めちゃくちゃ話題になってますよね。
何気なく見始めた人も
「え、なにこれ怖いんだけど…」
ってどんどんハマってる感じ。
舞台は、ある小学校の卒業アルバム。
そこに写っているのは6人の同級生──でもその顔が、黒く塗りつぶされてるんです。
ゾクッとしますよね。
で、その6人のうちのメンバーが、次々と“謎の死”を遂げていく。
「あれ、これただの同窓会ミステリーじゃないぞ?」ってなってくるわけです。
しかも恐ろしいのは、その裏にある“小学生時代の罪”。
当時、彼らはある過ちを犯していて、それをきっかけに1人のクラスメイトの人生がめちゃくちゃに…。
でもね、その子の存在を“みんな忘れてる”んですよ。
名前も顔も、まるで最初からいなかったかのように。
──そう、それが“7人目の博士”。
ある日、ネットの掲示板に現れた「博士だろ?」というメッセージから、全てが動き始めます。
視聴者としては、
「この博士って誰!?」
「なんでそんな大事な存在をみんな忘れてるの!?」
って気になって仕方ない。
この“忘れられた7人目”の存在こそが、物語を大きく揺さぶるキーパーソン。
ちなみに、ただの犯人探しじゃないです。
誰が悪くて、誰が正しいのか。そもそも“善と悪”って何?──そんな哲学っぽいテーマも潜んでいて、考えさせられることが多いんですよ。
そんなわけで──このドラマを理解するには、「7人目の博士」を知らずして語れません!
7人目の博士は誰?
さて、気になるのが“7人目の博士”って結局誰なの?って話ですよね。
ドラマ『良いこと悪いこと』の中でも、この謎の人物は一度も顔を出さず、名前すらはっきり語られていません。
なのに、物語の核心にガッツリ関わってくる──まさに“姿なき黒幕”みたいな存在です。
じゃあ、どんな手がかりがあるのか?
視聴者の間で注目されているのは、ある男の子の存在です。
名前は「堀遼太(ほり りょうた)」。
彼は小学生の頃、「昆虫博士になりたい」って夢を描いていた少年なんです。
そして物語が進む中で、この“昆虫博士の夢”が出てくる回想シーンが登場。
「え、これってまさか博士?」
と多くの視聴者がピンときたわけですね。
良いこと悪いこと
#5将来の夢の中で
『博士』が付くのは
『昆虫博士』しかいない… pic.twitter.com/IM2Rr2BiI7
— 小次郎➡️ゆず丸 (@kojikoji_to) November 8, 2025
良いこと悪いこと
4話でセミの抜け殻の話の時
3人ともバラバラで
ちょんまげ、カンタロー、ターボーって
それぞれ記憶してるけど
堀遼太くんのことじゃない?って思ったCM入る前、卒アル順に全員の夢が流れてて
堀くんの夢は昆虫博士だったのと
公式Xの卒アル写真右下の黄色の封筒?も
↓ pic.twitter.com/R61pseZ3Dg— koton (@s_saaaaa000) November 1, 2025
さらに、今作の重要キャラの1人である“スナック常連の今國(イマクニ)”が登場したことで、
「堀遼太=今國=博士では?」という説が浮上。
今國が話す内容には、ポケモンの話題や昆虫の話が混じっていて、ちょっとオタクっぽい。
でも、どこか寂しげで、過去に何かを抱えてそうな雰囲気があるんですよね。
これ、偶然だと思いますか?
実は彼、同窓会にも顔を出してないんです。
しかも他の登場人物も、「そんな人いた?」とピンときてない。
この“誰の記憶にも残ってない感じ”が、逆に怪しすぎるんです。
──ただし!
ここがこのドラマの面白いところなんですが、「今國=博士説」は“ミスリードかもしれない”という声もあります。
推理モノって、明らかに怪しい人物は逆に犯人じゃないってパターンありますよね?
それと同じで、わかりやすすぎる伏線には要注意。
たとえば、掲示板で「博士」と会話してたのは“ちょんまげ”こと羽立。
彼だけが博士のことを少し覚えていた様子なんです。
「覚えてるよ、博士だろ?」という一言──これ、実はかなり重いんです。
もしかしたら、羽立は博士と何か特別な関係があったのかもしれませんし、
「覚えてないフリ」をしてる他のメンバーとの対比を描いてるのかもしれません。
それと、もう一人のキーパーソンが担任だった大谷先生。
卒業アルバムから博士の痕跡を“意図的に”消していた可能性があるんです。
「え、それってつまり隠蔽?」と思った方、正解です。
先生が何らかの“悪いこと”に加担していたとしたら、それも博士が復讐を仕掛ける理由として筋が通りますよね。
良いこと悪いこと考察してみたら、、、
第1話のシーンが怖すぎる。担任の大谷先生
「このタイムカプセルは学校が創立50周年
を迎える2025年に掘り起こします」
↑
「掘り起こします」の部分だけ
22年後の大谷校長先生の声じゃね??#良いこと悪いこと #イイワル pic.twitter.com/5d7rd73z8I— 富山魂💙💙 (@toyama_damashii) November 8, 2025
このように、“7人目の博士は誰なのか”という問いには、いくつもの有力候補が浮上しています。
でも一番大事なのは、「なぜその人物が“忘れられていた”のか」という部分。
記憶から消えるって、普通じゃない。
誰かを無視する、見て見ぬふりをする──それって、ただのいじめよりもずっと残酷だったりしますよね。
この博士の正体に迫っていくことで、
私たち自身の中にある「誰かを傷つけた過去」や「なかったことにした記憶」にも、
向き合わされてしまうんです。
「もしかして、私も“誰かの博士”だったのかもしれない」
そんなゾワっとする余韻を残しつつ、次は──この“博士”というキャラクターが物語全体にどんな意味を持つのか。
もっと深く考えてみましょう。
博士の正体に隠された意味を考察
7人目の博士が“誰か”という話ももちろん気になりますが──
実はそれ以上に大事なのが、
「そもそもこの博士って、どうして名前だけの登場だったのか?」
という部分なんです。
普通なら、誰かを登場させるなら顔も見せて、性格も描いて…ってなるじゃないですか。
でも、この博士にはそれが一切ない。顔も出てこないし、声もない。
セリフも登場人物の口からしか語られない。
にもかかわらず、視聴者の印象には残りまくってるんです。
これってつまり、「博士=実在する人物」ではなく、
「物語の象徴」として描かれている可能性が高いんですよね。
たとえばですが、「沈黙の博士」という設定には、こんな意味が込められているとも考えられます。
他の6人の博士は、それぞれ“善とは何か”“悪とは何か”を議論したり、証明しようとしたりしています。
でも、7人目だけは何も語らない。
ただ静かに沈黙を貫いているんです。
これ、逆説的に「一番本質に近い存在」なのかもしれません。
だって、善も悪も人によって違うし、状況によっても変わりますよね?
白黒つけることが正義とは限らない。
もしかしたら、“何も言わない”という選択こそが、一番誠実だったりするのかも。
良いこと悪いこと考察
この方の意見に賛同すぎる
博士はポケモン、ゲーム、虫取りの絵
その繋がりから視聴者はイマクニって
思ってるけど、イマクニはヒントを出してるだけで
犯人ではない。
新キャラ、キングの娘の担任の先生が7人目濃厚#良いこと悪いこと #イイワル pic.twitter.com/HgQlsvUjAN— みおみおさぶあか【なんでもbot】 (@miomio_koya19) November 9, 2025
さらに興味深いのは、「7」という数字の意味。
7って、昔から“特別な数字”として扱われることが多いですよね。
七つの大罪、七福神、虹の色、音階、曜日…いろんな場面で「完全な数」とされてきました。
つまり、この7人目の博士が加わることで、物語の構造が“完成”するんです。
6人だけだったら、不完全。
でも「誰も知らない7人目」がいたことで、見えてくる「善と悪の本当の境界線」がある。
そんな構成になっているのかもしれません。
あと、「誰もが博士になりうる」って視点も外せません。
実際、制作側の意図として、「視聴者自身が博士になる」という仕掛けがあるとも言われています。
つまり、「博士は誰か?」じゃなくて、
「あなたが博士だったら、どう考える?」という問いが投げかけられてるわけです。
SNSでも、「自分も昔、あんな風に誰かを忘れたことがある気がする」といった共感の声が多く見られました。
「いなかったことにした記憶」
「都合の悪いものから目を逸らす心」。
それって、意外と誰の中にもあるんですよね。
そう考えると、博士は“あなた自身”の可能性もあるわけです。
視聴者がこの作品を通して向き合わされるのは、犯人探しよりも、むしろ“自分自身の内面”なのかもしれません。
ドラマを見ているつもりが、実は“見られていた”──そんな構造になっているのが、
この『良いこと悪いこと』という作品の奥深さ。
だからこそ、この博士は“顔がない”。
空白のままで描かれているんです。
その空白に、何を感じるかは人それぞれ。
でも、だからこそ引き込まれる。
だからこそ、考えたくなる。
このドラマにおける“博士”という存在は、ただの登場人物ではありません。
私たちが普段スルーしてしまいがちな
「曖昧な善悪」「忘れ去った記憶」「人間関係の見えない線」
を、そっと浮かび上がらせる鏡のような存在なのです。