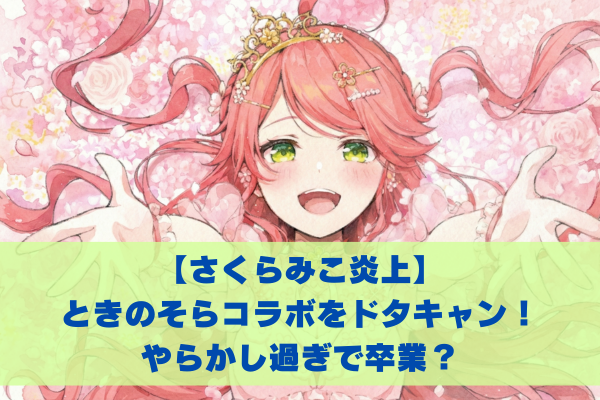ニュースを読んで、しばらく固まってしまいました。
1100匹ものコアラが、ヘリコプターから射殺されたなんて…信じがたい話ですよね。
場所はオーストラリア・ビクトリア州のブジビム国立公園。
山火事によって森は焼け、ユーカリの木も食べ物も消えてしまったとのこと。
コアラたちはやけどを負い、飢えて、すでに生きのびるのは難しい状況だったそうです。
それを受けて、州の当局は「安楽死が必要だった」と判断したらしいのですが…。
安楽死=銃殺という方法に、私はどうしてもすぐ、「仕方ない」と納得ができませんでした…
「これは仕方なかった」と言えることなのでしょうか?
このニュースについて感じた事を書いてみました。
目次
これは安楽死なのか?という問い
ビクトリア州政府は、コアラたちが深刻な火傷や飢餓状態にあり、「生存の可能性が非常に低い」と判断したと発表しました。
地上からの救護が困難だったこともあり、
「苦しませないための措置」として、空からの射殺が選ばれたということです。
たしかに、現場の状況や人員不足など、現実的な問題もあったのかもしれません。
それでも、「安楽死=銃撃」と聞いたとき、私はやはり強い違和感を覚えました。
空から見ただけで、どのコアラが助からないのか、本当に判断できたのでしょうか?
すべての個体が一瞬で命を絶たれたとは限りません。
苦しみを取り除くための行為だったはずなのに、
新たな苦しみを生む結果になってはいなかったか、気がかりでなりませんでした。
SNSでは悲しみと怒りが拡がった
このニュースはすぐにSNSで拡散され、
「虐殺じゃないのか?」という声があふれました。
「火災から生き延びたのに、人間の手で命を奪われた」
「なぜ救おうとせず、殺すという選択をしたのか?」
私自身も、こうした意見を目にして強くうなずきました。
もちろん、長く苦しむよりは…と、ある種の“理解”を示す人もいました。
それもひとつの考え方かもしれません。
でも、「これが最善の方法だったのか?」と聞かれれば、
どうしても首をかしげてしまいます。
「クジラは守ってコアラは殺すのか?」という矛盾
今回、もうひとつ印象的だったのが、「ダブルスタンダードでは?」という意見が多く出たことです。
ダブルスタンダードとは、状況や相手によって判断や対応が変わる、矛盾した考え方や態度のことです。
オーストラリアは、これまで日本の捕鯨に対して厳しい姿勢を取ってきました。
それなのに、自国の象徴的な動物であるコアラを射殺する――。
この事実を知ったとき、私の中にも違和感が生まれました。
「命の重さに差をつけていないか?」
「動物を守るという姿勢に、一貫性はあるのか?」
これは、単なる“国際批判”の話ではありません。
動物に対する私たちの価値観そのものを問い直すような問題だと思いました。
「苦渋の決断」とはいえ、説明は十分だったのか?
複数の動物保護団体は、今回の判断と手段について、
「透明性に欠ける」として調査を要求しています。
たとえば、オーストラリアの活動家クレア・スミス氏は、
「ヘリから個体の状態を判断することは現実的なのか」と疑問を投げかけました。
この言葉には、私も強く共感しました。
射殺が必要だったという意見も理解できます。
けれど、それを正当化するには、十分な説明と根拠が求められるはずです。
人間が命を奪うという判断を下すのなら、
その過程は徹底的に透明でなければいけない――そう思わされました。
背景にある「人間の責任」とは
ビクトリア州には約46万匹のコアラが生息しているとされています。
今回の射殺が行われた場所は、絶滅危惧指定のエリアではありません。
一方で、森林伐採や都市開発により、
野生動物のすみかが年々失われているのも事実です。
つまり、コアラたちが苦しむことになった背景には、
人間による環境破壊があるのです。
コアラの“数が増えすぎた”という報道も一部にありますが、
それを理由に命を奪うことが許されるとは思えません。
私たちは、自然に手を加えてきた責任から目を背けてはいけないのではないでしょうか。
命とどう向き合うか、私たちの課題
このニュースを知ってから、ずっと心がざわざわしています。
「これが本当に、避けられない出来事だったのか?」
「もっと他の選択肢はなかったのか?」
そんな問いが、ずっと消えません。
誰かを責めたいわけではありません。
でも、命の重みや、生きるということの意味を、
もう一度真剣に考えるきっかけになったのは確かです。
遠い国の話かもしれません。
けれど、私たち一人ひとりがこの問題に目を向けていくことこそが、
未来の命を守る第一歩なのではないでしょうか。