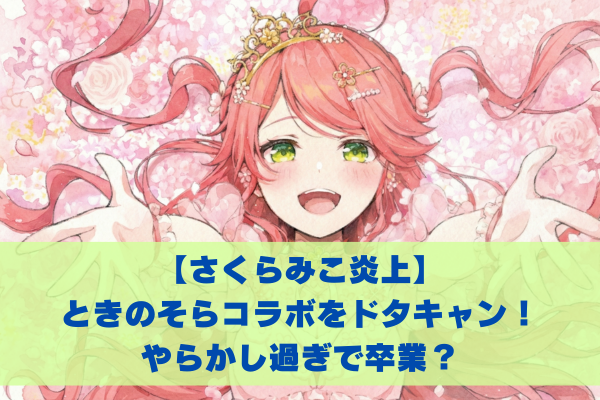9月末に放送された日テレ「news every.」の奈良公園特集が、思わぬ注目を集めています。
画面に映ったのは、オレンジ色の制服を着たバスガイド風の女性。
そして、限られた2人の証言。
報道の焦点は「外国人観光客のマナー問題」だったはずですが…。
なぜか、視聴者の関心は出演者の“正体”や“構成の偏り”に移ってしまったのです。
番組の意図とは裏腹に、SNSでは“やらせ”や“偏向報道”という言葉が飛び交う事態に。
報道に対する信頼のあり方が、静かに、けれど確実に揺らいでいます。
何が起きたのか?
そして、なぜここまで話題になってしまったのか?
その背景には、私たちが見落としがちな「報道の見せ方」があるのかもしれません。
日テレ鹿報道に広がる疑問
2025年9月29日に放送された、日テレ「news every.」の奈良公園特集。
当初は、自民党総裁選に立候補した高市早苗氏の発言を検証する目的で組まれたものでした。
高市氏は演説で、

と問題提起。
その発言に対して、一部からは「外国人ヘイトでは?」という批判も出ていました。
こうした背景のもと、番組は奈良公園での現地取材を敢行します。
取材に登場したのは、25年商売をしているという飲食店オーナーと、ガイド歴10年以上の女性の2人。
この2人って本当に奈良県在住、奈良公園の状況知ってるの?コロナの時にガンガン出たクライシスアクターみたいなサクラじゃないよね?#奈良公園#奈良の鹿 pic.twitter.com/gQDXsjZril
— 🇯🇵小波桜🌸 (@STI2026) September 29, 2025
2人とも
「鹿への暴力は見たことがない」
「外国人観光客はむしろフレンドリー」
と証言していました。
番組はこの2人の意見をもとに、「暴力の証拠はない」と結論付ける流れに。
しかし、ここでSNSがざわつき始めます。
- 「たった2人の証言で何がわかるの?」
- 「なぜ他の関係者に取材しない?」
疑問の声は瞬く間に広がっていきました。
注目されたのは、飲食店オーナーの証言です。
実はこの店舗「牛まぶし三山」は、奈良公園の様子が見える位置にはないという現地の証言がありました。
SNSでは「公園が見えないのに、鹿の様子を語れるの?」といったツッコミが飛び交いました。
また、一方では25年勤務をしている事は事実であり、証言に関して信憑性は高いのではないか?
という声もあるようです。
牛まぶし三山の料理長らしい。
日テレの元動画はインタビューシーンがカットされてしまったのでどの様に紹介されたか確認出来ないが、中卒で修行の道に入ったなら”飲食店25年”は有り得る。https://t.co/KqHDRTSOqm https://t.co/NwtFreHz2l pic.twitter.com/W8Id7RrIlU— 徳川昇(仮名) (@BlueSkyBlue67) September 30, 2025
さらに、もう1人のガイド女性の“正体”にも注目が集まります。
名前や所属が明かされないまま放送され、番組後にSNSで検証が始まりました。
- 「見たことがない」
- 「ガイド団体の制服と違う」
との声が上がり、「やらせでは?」という疑念まで浮上します。
加えて、日テレの公式YouTubeでこの女性のインタビュー部分だけが削除とされたという報告も。
この動きが、さらに視聴者の不信感をあおる形となりました。
X(旧Twitter)では、「#奈良公園のガイド」「#クライシスアクター疑惑」などのタグが拡散され、
関連投稿の表示回数は500万回を超える事態に!
結果、焦点は高市氏の発言そのものよりも、
- 「日テレの報道姿勢」
- 「番組構成の偏り」
に集まるようになっていきました。
なぜこの2人だけに取材したのか?
他の立場の意見はなぜ紹介されなかったのか?
今や情報は一方向に流れる時代ではありません。
報道に求められるのは、バランス・透明性・そして“誰の声を拾うか”という慎重な判断です。
オレンジ服バスガイドは誰?
「news every.」の奈良公園報道で、視聴者の関心を最も集めたのが“オレンジ色の服を着たガイド女性”です。
番組内では「ガイド歴10年以上」と紹介されていましたが…。
放送後、SNSでは
- 「誰?」
- 「どこのガイド?」
と素性をめぐる疑問が一気に噴出しました。
注目されたのは、Z李(@ShinjukuSokai)氏の9月30日の投稿です。
彼は、「この女性の所属会社のインスタを発見した」と投稿。
このガイドさんの会社のインスタ見つけた。
この人は本当に奈良でガイドやってる歴史ナビゲーター会社のスタッフさんで、10年近く前からインスタやYouTubeで鹿の写真や動画をアップしてる人たちだった。
他のスタッフもオレンジ色のユニフォーム。
アルミホイラーたち大丈夫か? pic.twitter.com/vQba0x1Z2h— Z李 🇺🇦 NO WAR 🕊 (@ShinjukuSokai) September 30, 2025
その企業は奈良で約10年観光情報を発信している会社で、他のスタッフも同じようなオレンジの制服を着ていたと主張しました。
ただし、会社名は明かされておらず、投稿内容の検証は進んでいないのが現状です。
一方、10月1日には奈良市議のへずまりゅう氏が現地で直接取材を行いました。
その結果、「この女性は人力車ガイドとして2年勤務している」との証言が確認されたと報告。
また、日テレ側が取材の趣旨をきちんと伝えていなかった可能性も指摘されています。
【ご報告】
日テレ偏向報道についての最新情報。
まずガイド10年の表記については間違いで取材に応じた女性は2年間人力車のお仕事をされております。
次に質問内容の主旨も受けていなかったとのことです。
人力車も飲食店も仕事で忙しいのに鹿さんが暴力を振るわれてる姿なんて見れる訳ないでしょ。… pic.twitter.com/Gatw4d8hJ9— へずまりゅう (@hezuruy) October 1, 2025
つまり、“10年以上のガイド歴”というテロップと、実際の勤務歴には大きなズレがあったのです。
このズレが、さらなる不信を招く結果に。
制服についても議論が続いています。
奈良公園のガイド関係者10名以上が「見たことがない」「団体の制服とは違う」と証言。
しかし、Z李氏は「特定企業の制服と一致している」と反論。
現地証言とネット検証が真っ向から食い違っている状況となっています。
そんな中、過去の番組に出ていた女性と似ているとして、クライシスアクター疑惑も浮上。
AI顔認識ツールでの“高一致率”を報告する投稿も見られました。
どう見ても同じ女性ですよね。
日テレと自民が協力してヤラセをしているのでは?#クライシスアクター疑惑#奈良公園のガイド
ステマ問題に高市氏への誹謗中傷から何も学んでいない。 pic.twitter.com/17fwFkbkrm
— サイン (@Shg5Acnt76KOSgH) September 30, 2025
ただ、Z李氏の投稿以降、「陰謀論」的な声はやや減少傾向に。
今では「誰なのか?」という点より、「情報の矛盾」や「放送の信頼性」に焦点が移っています。
ちなみに、番組では「奈良公園のガイド」と紹介されていましたが、
SNSでは「バスガイドでは?」「人力車のスタッフでは?」といった複数の説が浮上。
へずまりゅう氏の取材では、「人力車ガイドとして2年勤務」との証言が得られました。
Z李氏の主張する企業が実在するとしても、本当に観光業に10年関わっているかは不明です。
しかも、同社からの正式なコメントは今も出ていません。
【追記】
その後、注目されたのが10月1日のあるポスト。
X上で「心家」という観光会社の代表を名乗る松田氏が、新しくアカウントを開設しました。
その投稿が話題になりました。
日本テレビnews every.のインタビューを当社従業員が受けたことについて。
現在SNSでは、当社従業員が、日本テレビがインタビューのため準備した人物としての疑惑を向けられ数万件を超える拡散をされています。
インタビューについて。
本人は番組の主旨説明は受けておらず、外国人観光客への印象と— 松田 (@YRalNBPnC850273) October 1, 2025
投稿の中で松田氏は、番組に登場した オレンジ色の服を着た女性は、心家のスタッフであると明言。
彼女は、バスガイドやホテル勤務の経験があり、現在は奈良公園の観光ガイドとして2年間勤務していると説明しました。
また、インタビュー時に番組の主旨がきちんと伝えられていなかった とも主張。
その結果、女性はSNS上での過剰な詮索にさらされ、心身に深刻なダメージを受けている といいます。
一方で、奈良市議のへずまりゅう氏は、現地で直接取材を実施。
その中で「人力車ガイドとして2年勤務 している」との情報を伝えています。
さらに彼もまた、日テレ側の 取材趣旨が十分に伝わっていなかった可能性 を指摘しました。
松田氏の説明と一部一致しているものの、業種にズレがある点がSNSで注目 されています。
こうした経緯を受けて、SNSでは「やらせではなかったのか?」とする擁護の声が増えてきました。
しかし同時に、
- 「心家という会社の詳細が不明」
- 「新しく作られたアカウントは不自然では?」
といった疑問の声も続いています。
いわゆる「クライシスアクター説」や「完全なやらせ」など、極端な憶測は弱まりつつある ものの、
議論自体はまだ収束していないようです。
結果として、ガイド女性の正体は“特定されたようで、されていない”。
そして、真相を明かすはずの報道が、逆に新たな混乱を生んでいる――そんな状況が続いています。
偏向報道とやらせ疑惑の真相
今回の日テレ「news every.」奈良公園特集が炎上した理由。
それは内容そのものよりも、“取材の姿勢”や“放送の構成”に対する強い違和感にあります。
まずは、取材対象はたった2人。
そのうちの1人(ガイド女性)は、放送後にSNSで正体が疑われました。
そして、10月1日には奈良市議・へずまりゅう氏の現地取材で、「人力車ガイドとして2年勤務」と特定されたのです。
しかし、番組では「ガイド歴10年以上」と紹介されていたため、“情報の食い違い”が指摘される結果に。
もう1人の飲食店オーナーについても、疑問が広がっています。
店舗は「牛まぶし三山」。
へずまりゅう氏の取材やSNS上の情報によれば、店の立地からは奈良公園の様子が見えないとのこと。
そのため、
- 「どうやって鹿の行動を見たのか?」
- 「公園が見えないのに“暴力は見たことない”と断言できるのか?」
という声が多く寄せられました。
また、見逃せないのが、“番組で触れられなかった証拠”の存在です。
SNS上には、外国人観光客が鹿を蹴る動画が過去に複数拡散されています。
特に注目されたのが、奈良市議・へずまりゅう氏による鹿パトロールの記録動画です。
【拡散希望】
これは酷すぎる。
この中国人は子供の目の前で鹿さんを傘で叩きました。
鹿さんの反応をよく見て下さい。
これは動物虐待であり絶対にあってはなりません。
へずまりゅう軍団の一員がパトロールをし注意してくれました。
奈良の治安維持は僕達に任せて下さい。 pic.twitter.com/VAolYX6Vw1— へずまりゅう (@hezuruy) August 29, 2025
雨の日は傘が武器になります。
中国人は傘で鹿さんを叩き突きます。
何度も言いますが日本の天然記念物が傷付けられているのに罰金を取らないのは何でなんですか?
自分は市長の検討するという言葉を今も信じております。 pic.twitter.com/rmYL4ds5Sv— へずまりゅう (@hezuruy) October 5, 2025
これらの動画や画像は多くの人の目に触れています。
それでも番組では一切取り上げられず、視聴者からは
- 「偏った編集だ!」
- 「なぜこの動画は無視されたの?」
と、批判の声が高まりました。
さらに、火に油を注いだのがYouTubeでの動きです。
日テレ公式チャンネルにアップされた動画から、ガイド女性のインタビュー部分のみが削除されたと多数報告されています。
なぜその部分だけ消したのか?
説明がないまま編集され、結果的に「何か隠しているのでは?」という憶測を生むことに。
SNSでは、
「#偏向報道」「#やらせ疑惑」「#日テレ」「#クライシスアクター」などのハッシュタグが一斉にトレンド入り。
番組が「やらせ」だったと断定できる証拠は出ていません。
それでも、
- 「なぜこの2人にしか取材しなかったのか?」
- 「他の立場の声をなぜ拾わなかったのか?」
という疑問は今も残ります。
一方で、「やらせではなく、構成が雑だっただけでは?」という冷静な見方も一部にはあります。
しかし、視聴者の不信感はそう簡単には消えません。
今の時代、視聴者はただ放送を見て終わるだけではありません。
SNSで検証し、過去の情報を掘り起こし、“編集の意図”にまで目を向けるようになっています。
情報の出し方ひとつで、「報道」が「疑惑」に変わる時代。
だからこそ、メディアには今まで以上に、透明性と説明責任が求められているのではないでしょうか。
まとめ
今回の日テレ「news every.」の奈良公園報道は、単なるテレビ番組の一場面を超えて、大きな社会的議論へと発展しました。
出演者の信頼性、取材の偏り、削除された映像…。
それぞれがバラバラのようでいて、「報道のあり方」そのものを問う材料となっています。
確かに、やらせだったのか、偏向報道だったのか――。
その答えを現時点で明確にすることは難しいかもしれません。
けれども、今回の騒動を通じて明らかになったのは、
私たち視聴者が“情報を鵜呑みにしない時代”に生きているということです。
SNSを通じて、誰もが検証し、拡散し、議論できる時代。
報道には、これまで以上に説明と透明性、そして多角的な視点が求められています。
もしかすると、この一件が、メディアの姿勢を見直す大きな転換点になるかもしれません。
それは、視聴者の“疑う力”が、ようやく本領を発揮し始めた証なのかもしれませんね。